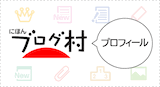「老い」が気になり始めたあなたへ。
鏡に映る顔、肩こり、スマホの文字が見えにくい…そんな“小さな老い”が積み重なる日々。
だけど、みうらじゅんの「老三段活用」を知ったら、ちょっと笑えて、肩の力が抜けるかも?
この記事では、みうらじゅんの『老いるショック』『老けづくり』『アウト老』という三部作(勝手に命名)を語りながら、老いをユーモアに変えるヒントを紹介します。
第1章:好きすぎる。ついに完結?老三段活用
みうらじゅんがまた来ている。
なんなら、いま一番「老い」を面白がってる67歳かもしれない。
私は以前から彼の“なんでもマイブーム”なスタンスが好きだったけど、このところの展開はズルい。
『老いるショック』『老けづくり』、そして『アウト老』──この三つの言葉に、どうしようもなく惹かれてしまった。
これはまるで、「老い」という避けがたい現実に、笑いと知恵で立ち向かう“じゅん流・老三段活用”。
読んだら妙に腑に落ちるし、自分の毎日もちょっと肯定された気がする。
第2章:「老いるショック」〜これは身体的反応である〜
まず、老いのスタート地点として記録されるのが「老いるショック」である。
これは、ある日突然鏡に映る自分の顔が、「誰?」となる現象。
また、スーパーで読もうとした成分表示がボヤけたり、朝イチの膝が鳴る、
などの“軽度の加齢現象”も初期症状として多く報告されている。
重要なのは、みうらじゅん氏がこの段階を“ショックとしてちゃんと扱った”ことだ。
そう、我々は驚いていいのだ。
これは「加齢性サプライズ」であり、放置すれば“自己否定”に発展することもある。
ショックは事実。だが、悲しみではない。
それをみうら氏は“笑いの導入剤”に変換した。ここにリスペクトしかない。
第3章:「老けづくり」〜“老”はアートである〜
ショックの次に来るのが「老けづくり」である。
これは極めてみうら的な逆転発想である。
老いを嘆くのではなく、「あえて老けてみせる」という演出。
つまり、老いを自分でコーディネートするスタイル。
「え、意外と若いですね」という副産物。
研究対象として重要なのは、ここに“能動性”が生まれること。
「自然に老けていく」のではなく、「老ける自分をプロデュース」するというフェーズに突入するのだ。
私たちに落とし込んでみよう。
髪を染めずにグレイヘアを活かす。
派手すぎない眼鏡で“知的枯れ感”を演出。
昼間から湯のみでお茶を飲みながら、卓上カレンダーにちょっとした名言メモ。
これ全部、老けづくりである。
つまり、老けるというより「いい老け感を作る」という知的作業。
これをひとつの“アート”として提示したみうらじゅん氏、やはり只者ではない。
第4章:「アウト老」〜老いに自由を与えよ〜
老けづくりを経てたどり着く、最終段階が「アウト老」である。
これは、これまでの常識的な“シニア像”から逸脱することで得られる、精神的自由のことである。
「“老けづくり”の延長に“アウト老(アウトロー)”という新ジャンルを作った」との事。
そう、それだけで“制度の外”に出られる。
「老人はこうあるべき」「そろそろ落ち着かないとね」といった社会からの圧に対し、
“アウト老”という言葉は逆に突き抜ける力を持っているのだ。
私たちに落とし込んでみよう。
昼から銭湯に行き、夕方に餃子とビールで反省会をしてもいい。
昔ハマってたパンクバンドを今さら聴き直して、またTシャツを買ってもいい。
孫の話ばかりせず、むしろ「推し活」に夢中でもいい。
それらはすべて「アウト老」の営みであり、他人の評価軸から離れた自己肯定の実践なのだ。
“老い”に“アウト”をつけた瞬間、人生はまた面白くなる。
これは、みうらじゅん流・老いの最終奥義といえよう。
終章:そして私は、アウト老を志すことにした
以上の三段階──「老いるショック」「老けづくり」「アウト老」──を経て、私は一つの結論に至った。
老いとは、
・驚きであり、
・試行錯誤であり、
・そして最後には、笑って突き抜けるものだ。
みうらじゅん氏の提案は、決して「気楽にいこうよ」と軽く流すものではない。
むしろ、真面目に老いと向き合ったからこそ見える景色。
そのうえで“ふざける”。これはもう、高度な知性である。
私もこれからは、老いを研究する側の人間として生きていきたい。
老いに驚き、工夫し、最後にはちょっとアウトで笑う──そんな“老三段活用”を、
自分なりに実践してみようと思う。
次回の研究テーマは「老後の趣味に“ひとりパンク”はアリか?」。
それまでは、銭湯でビールでも飲みながら考えることにする。
またね!
※アイキャッチには、イラストACのエトユニグラフィックさん(作者ページ)の素材を使用しています。
📣応援してもらえると助かりんこ。にほんブログ村